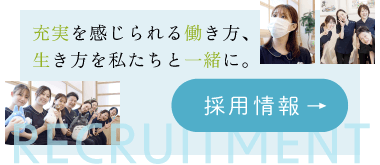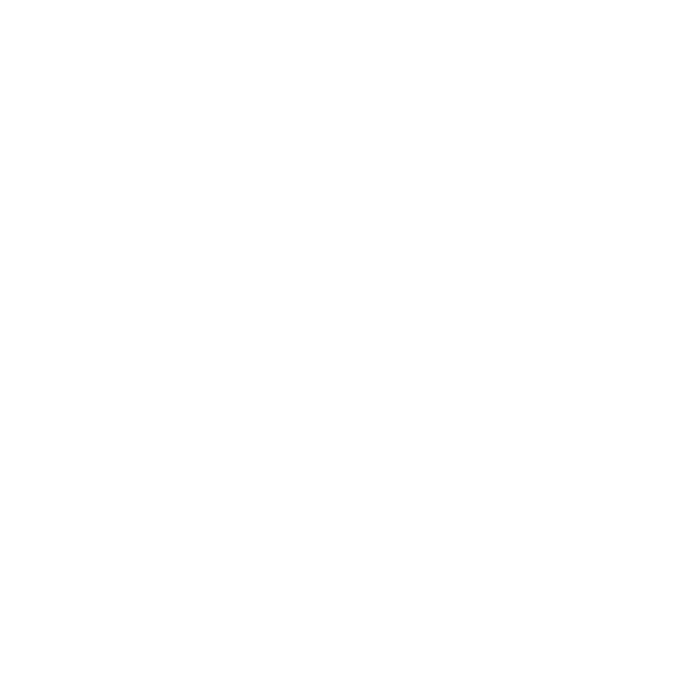血便が出たとき、人が感じる不安と判断の難しさ
排便後に便器を見たとき、赤い血が混じっていた――。そんな経験をしたことがある方は少なくないでしょう。
「たった一度のことだから大丈夫」「よくあることだから様子を見よう」と自己判断してしまう方も多くいらっしゃいます。
しかし、血便という症状には、放置してはいけない重大な病気が潜んでいる可能性があります。
本記事では、血便の種類、考えられる原因、受診すべきタイミング、必要な検査や治療法、そして予防方法まで、専門的かつ丁寧に解説していきます。
腸の異常を見逃さず、早期に対処することの重要性を、医師の視点からお伝えします。
血便とは何か?医学的な定義と種類を解説
血便とは、その名の通り「血が混じった便」を指しますが、その色や量、混じり方によって、血が出ている部位や原因となる病気が異なります。
血便の色でわかる出血部位
鮮やかな赤色の血便は、主に肛門や直腸に近い場所からの出血が疑われます。
一方、黒っぽい便(いわゆるタール便)は、胃や十二指腸などの上部消化管からの出血であることが多く、胃潰瘍や胃がんが原因の可能性も否定できません。
また、赤黒い血が混ざっている場合には、S状結腸や下行結腸など中間部の腸からの出血が考えられます。
便の色をしっかり観察することで、出血源の特定につながる重要なヒントになります。
「一過性の出血」か「繰り返す出血」か
1回だけの出血でも、腸内にポリープやがんなどの病変が隠れていることがあります。
特に、普段は便の色に異常がないのに急に血便が出た場合や、血の量が多い場合には要注意です。
血便が出る仕組み
腸は大きく分けて小腸と大腸に分類されますが、血便の原因のほとんどは大腸にあります。
出血は、腸の内壁が炎症を起こしたり、傷ついたり、腫瘍ができたりすることで起こります。
また、痔による出血も非常に多く見られますが、自己判断で「痔だろう」と決めつけることは危険です。
痔と思われていた出血が、実は直腸がんであったというケースも珍しくありません。
血便の原因には何があるのか?代表的な疾患一覧
肛門疾患による出血(痔核・裂肛など)
最も多い原因のひとつが痔による出血です。
排便時に強くいきんだり、硬い便が肛門を傷つけたりすることで出血が起こります。
血の色は鮮やかで、便に血が付着する、もしくは便器の水が赤く染まる形で現れます。
大腸ポリープ
大腸の粘膜にできる良性の腫瘍であるポリープは、大きくなると便の通過時に傷つきやすくなり、出血することがあります。
多くは無症状ですが、放置しておくと大腸がんへと進行するリスクもあります。
大腸がん
特に中高年に多く、初期は無症状のこともあります。
出血が少量でも、がんの兆候であることがあり、血便は大腸がん発見の重要なサインとなります。
便が細くなったり、排便回数が増減したりする場合も注意が必要です。
炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎・クローン病)
10代~30代の若年層にも発症することがある病気で、腸粘膜に慢性的な炎症が生じます。
しぶり腹や粘液便、血便が繰り返され、治療を怠ると腸に潰瘍や狭窄を形成することもあります。
感染性腸炎
細菌やウイルスが原因となり、一過性の激しい下痢や血便を引き起こします。
発熱や腹痛、嘔吐を伴うことが多く、脱水症状にも注意が必要です。
他にもある血便の原因とその特徴
- 虫垂炎(盲腸)により大腸に炎症が波及した場合
- 虚血性腸炎による一過性の粘血便(特に高齢者に多い)
- 放射線性腸炎(がん治療後の合併症)
- 内痔核の脱出や肛門周囲膿瘍による出血 など
他の症状を伴う血便には特に注意を
血便が現れた際、それが単独の症状なのか、あるいは他の体調変化を伴っているのかによっても、緊急度は大きく変わります。
たとえば、血便とともに激しい腹痛や発熱を感じている場合、感染性腸炎や炎症性腸疾患が疑われることがあります。
これらは適切な治療を受けなければ症状が悪化する可能性があるため、早急な受診が勧められます。
また、排便回数の増加や便の形状の変化、体重の急激な減少、慢性的な倦怠感などが伴う場合には、大腸ポリープや大腸がんの存在も視野に入れる必要があります。
とくに痛みを伴わない静かな血便は、大腸がんの初期兆候であることがあり、注意深く観察すべきサインといえます。
血便が出たときに自分でできるセルフチェック
実際に血便を経験したとき、「どのように医師に伝えればいいのか分からない」という方も多くいらっしゃいます。
そんなときに重要なのが、血の色、出血の量、出るタイミング、繰り返しの有無といった情報を可能な範囲で記録しておくことです。
たとえば、便の表面に血が付着しているのか、それとも便の中に混ざっているのか。
また、血の色が鮮やかな赤色なのか、赤黒いのかといったことも、医師が出血部位を推定するうえで大きな手がかりになります。
さらに、排便中に痛みを感じたかどうかや、出血以外の異変(腹痛や嘔吐など)があったかどうかも記録しておくと、受診時にスムーズな診断につながります。
可能であれば、異変を感じた日から数日間、排便の様子や体調の変化を日記のように記録しておくのもよいでしょう。
医療機関ではどのような検査を行うのか
血便の診察では、まず問診と視診が行われます。
問診では、いつから出血があるのか、どのような便だったのか、その他に体調の変化があったかなどを丁寧に聞き取ります。
その上で、肛門周囲の状態を確認するための視診や、指による直腸診、必要に応じて肛門鏡による観察が行われます。
これにより、痔や直腸の異常が早期に確認されることもあります。
次に行われるのが便潜血検査です。
これは、便の中に含まれる血液を化学的に検出するもので、肉眼では分からない微量の出血でも確認できるのが特徴です。
ただし、便潜血検査は「出血があるかないか」を判定する検査であり、その原因まで明らかにすることはできません。
出血の原因を特定するには、大腸カメラ(下部消化管内視鏡検査)が必要になります。
肛門からスコープを挿入して大腸の中を観察することで、ポリープや潰瘍、がんなどの病変を直接目で確認できます。
また、必要があればその場で組織を採取し、病理検査に回すこともできます。
大腸カメラでわかること、わからないこと
大腸カメラ検査では、大腸の粘膜を詳細に観察することができます。
腸内の小さなポリープや炎症所見も見逃さずに確認できるため、血便の原因精査としては最も有効な検査の一つです。
特に、がんや前がん病変である腺腫性ポリープの早期発見・早期切除には不可欠な検査といえるでしょう。
一方で、大腸カメラだけでは小腸の奥や、上部消化管の異常は確認できません。
原因が小腸にあると考えられる場合には、カプセル内視鏡や小腸内視鏡、上部内視鏡検査(いわゆる胃カメラ)などの追加検査が必要となる場合もあります。
原因が特定された後の治療法はどうなるのか
血便の原因が明らかになったあとは、それぞれの疾患に応じた治療が行われます。
痔の場合は、便通の改善や外用薬による保存療法が基本ですが、出血を繰り返す場合や、痔核が大きくなっている場合には、日帰りでの切除術が検討されることもあります。
ポリープが見つかった場合には、その場で内視鏡的切除を行うのが一般的です。
切除したポリープは病理検査に回され、がん化の有無を調べることになります。
良性であれば、再発防止のために定期的な検査が推奨されます。
炎症性腸疾患に対しては、5-ASA製剤やステロイド、免疫調整薬といった内服薬によるコントロールが中心となります。
感染性腸炎の場合には、原因となる菌やウイルスに応じた対症療法や抗菌薬治療が行われます。
大腸がんが疑われた場合には、さらなる画像検査や内視鏡的精査を経て、病期に応じた手術や化学療法などの総合的な治療計画が立てられます。
血便を予防するためにできる生活改善策
血便の予防には、腸内環境を整え、出血の原因となる疾患を未然に防ぐことが重要です。そのためにはまず、便秘や下痢を繰り返さないよう、毎日の食生活を見直すことが必要です。
食物繊維が豊富な野菜や果物、海藻類を積極的に摂取することで、腸の動きが促され、腸内の不要物がスムーズに排出されるようになります。また、発酵食品に含まれる善玉菌は腸内フローラを整え、炎症やがんのリスクを抑える効果があるとされています。
加えて、水分の摂取も非常に大切です。
脱水状態では便が硬くなり、排便時に肛門や直腸を傷つけてしまうことがあります。
1日1.5~2リットルを目安に、こまめに水分を補うよう心がけましょう。
そして、ストレス管理も見逃せません。
自律神経は腸の蠕動運動と深く関係しており、強いストレスは便秘や下痢の原因となります。
十分な睡眠、適度な運動、趣味やリラクゼーションの時間を意識的に取り入れることも、腸の健康には欠かせない要素です。
当院の内視鏡検査体制とサポート内容
当院では、血便のご相談に対して速やかに対応できる体制を整えております。
内視鏡専門医が在籍し、患者様一人ひとりの症状や不安に寄り添いながら、的確な検査と診断を行っています。
大腸カメラ検査では、鎮静剤を用いることで「眠っている間に終わる」苦痛の少ない検査を実現しています。
検査後は、内視鏡画像をもとに、わかりやすく丁寧な説明を心がけており、必要に応じてポリープのその場切除も対応可能です。
また、生活習慣の改善や再発予防のための指導にも力を入れております。
栄養指導、排便習慣のアドバイス、定期的なフォローアップ検査のご案内などを通して、患者様が長く健康な腸を保てるよう支援しています。
まとめ たとえ一度でも、血便は体からの大切なサイン
「たった一度の血便だったから」「痛みもなかったから」といって、見過ごすことは非常に危険です。
血便は腸のどこかで何か異変が起きていることを知らせる重要なサインであり、場合によっては早期のがんや重篤な疾患の兆候であることもあります。
自分自身の体の声に耳を傾け、小さな異変を見逃さないことが、健康を守る第一歩です。
血便が出たら、回数に関係なく、まずは医療機関に相談してください。
早期に原因を突き止め、必要な対策を講じることで、大きな病気を未然に防ぐことができます。
当院では、腸の病気に精通した内視鏡専門医が、皆さまの不安に真摯に向き合い、最善の医療を提供いたします。
どんなに些細なことでも、どうぞお気軽にご相談ください。